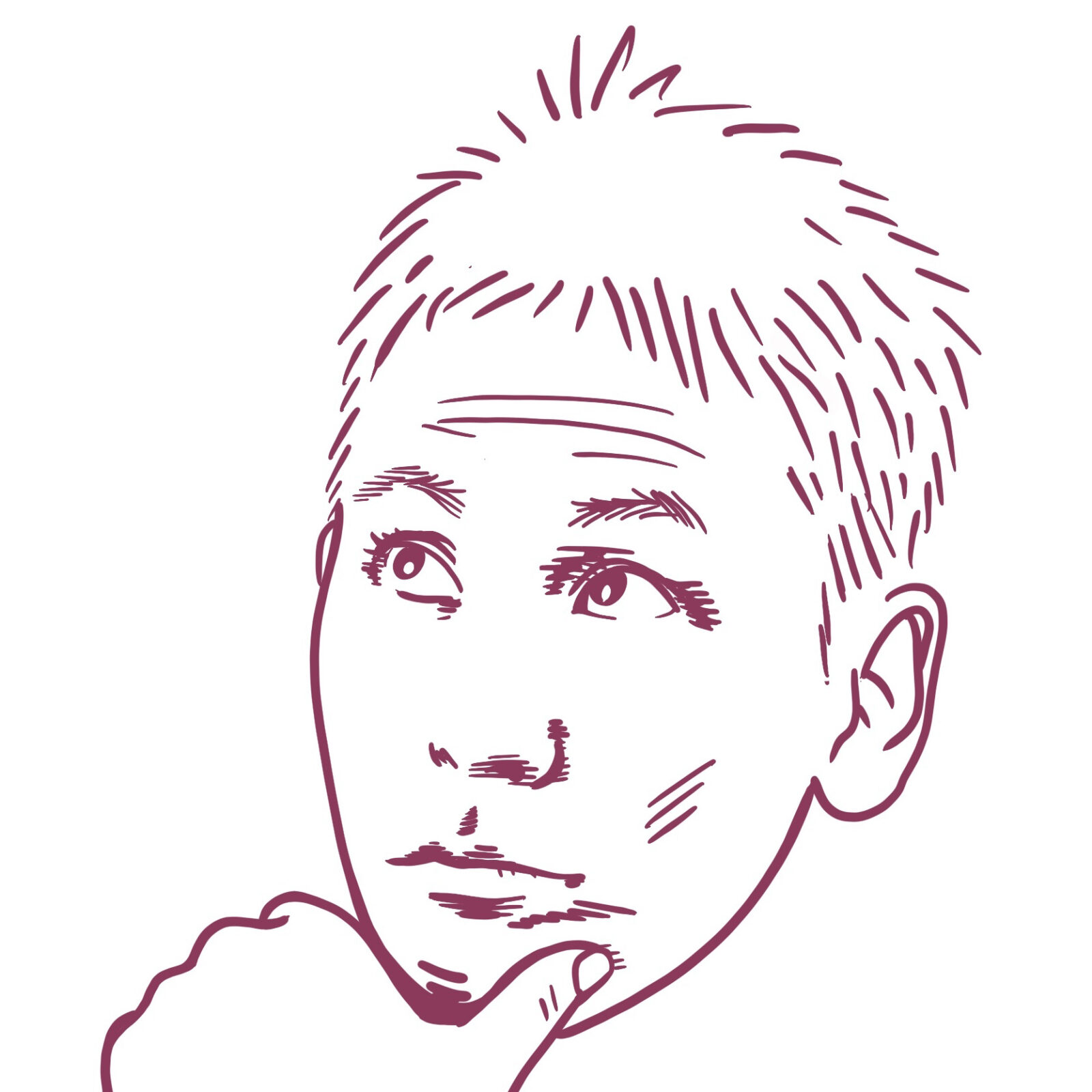「スタッフが登り、スタッフが撮る。」そんな写真を使ったロストアローらしい雑誌広告が続いています。ここ「BEHIND THE SCENES」でご紹介するのは、広告で使うための、というかただただ最高のショットを求めて奮闘したスタッフたちの汗と笑いにまみれたクライミング記。今回は、『ROCK&SNOW』2025年春号に掲載されたルート「判官贔屓」のストーリーを、登った本人の中嶋渉(物流部スタッフ)が綴ります。「開拓」というコスパ・タイパと対極にあるクライミング、その愉しみとは——。
悩める僕と五十島くん
「渉さぁん、なんかイイのないですかぁ?」
月に一度くらい、会社で顔を合わせるたびにそう聞いてくる五十島くんは、いつも目尻が下がっている。
「目尻を下げる」とは満足げに微笑むとか、魅力的な相手に見とれるという意味らしいけれど、五十島くんの場合はもともと目尻が下がり気味だ。
会社一の高身長である彼が、そんな様子で数十センチ上空から声をかけてくると、何かに忙しくなっているときでも手を止めてそちらを向いてしまう。
「イイの」というのは、例の広告写真に良さそうなネタということだ。「スタッフが登りスタッフが撮る」というコンセプトはいいとして、これが商品やブランドではなく会社そのものの広告だというから、どうにも難しく思えてくる。
「いやー、今はちょうどトライ中のプロジェクトもないしな」
個人的に、登山やクライミングの写真は好きだ。この広告写真の企画にも、とてもアツいものを感じていた。
それでも、ディレクターの半田さんとカメラマンの五十島くんは二人とも目が肥えていて、そうそう首を縦には振らないだろうな…と勝手に妄想する。
そしてただでさえ項目の少ない僕の「提案できそうなものリスト」は、しゅわしゅわと音を立てて縮んでいってしまうのだった。
そんな僕の小さな悩みを知ってか知らずか、熱心なクライマー社員数人を集めて企画会議を重ねた末に、「次回は渉くんをモデルに撮ります」という話になった。
これは困った。撮影場所や登るルートについて、ああでもないこうでもないと議論を重ね、いくつかの案が出ては消えた。
腕組みをしてうんうんと唸っていたときに、ある岩場のことをふと思い出した。
「実はひとつ、こういう岩場があるんですが…」
そうして提案してみたのが、今回足を運んだY岩(仮称)だ。

父とY岩
長野県の東部、特に佐久市近郊には、凝灰岩の岩場が点在している。長野県出身の僕は、この土地にいろいろな思い出がある。
クライミングを始めたばかりの頃、父に連れられてよく登りに行った。僕が自然の中でのクライミングに出会い、のめり込んでいくきっかけになったフィールドのひとつだと思っている。
数年前に帰省したときだったと思う。
「新しい岩場を見つけた」
僕をこの世界に引き込んだ張本人である父が、地図を片手にそう声をかけてきた。後日、父が目星をつけた山へふたりで偵察に行くと、馴染みのある見た目の凝灰岩の岩場が現れた。それがY岩との出会いだった。
僕の父・岳志は登山とクライミングを40年以上続け、長野県内を中心にいろいろな岩場に足跡を残す人物だ。さすがに最近は登るペースがかなりゆっくりになった気がするけれど、いまだに時間があれば山へ岩へ、とにかくあちこち出かけている。
クライミングと名の付くものはなんでもやってきた父だが、「開拓」と呼ばれる類のクライミングがなにより好きなようだ。「開拓」とは、一言で言えば、まだ誰も登っていない岩に新しいルートを見出して登る(初登攀する)ことだ。
大抵の場合、野山や渓谷にある手つかずの岩は植物、地衣類、泥や埃に覆われている。そのままの状態では登ることが難しかったり、危険だったりすることもあるため、実際に登る前に掃除をすることが多い。

手がかりとなる岩の凹凸を覆い隠す苔を磨いて落としたり、割れ目に詰まった土をかき出したり、これがなかなか骨の折れる作業だ。それを数十メートル、あるいは数百メートルの岩壁に見出したルートでやるのだから、数時間どころか丸一日かかっても終わらないこともしばしば。
それなのに、すべての下準備を終えて新ルートに取り付いて、ほんの数分でクライミングが終わってしまうことだってある。言ってしまえば、開拓とはとても泥臭いタイプのクライミングなのだ。
そんな父にクライミングを教わったからか、僕は僕でいつの間にか、荒れ地を耕すがごときこの種のクライミングが好きになってしまった。コンペティションとか、もっと華やかなクライミングを好きになって活躍していたらな…と思わなくもないけれど、好きになってしまったものは仕方がない。「血は争えない」とは、まさにこのことだ。
Y岩を見つけてからというもの、父はパートナーが居ても居なくても、足しげくこの岩場に通うようになった。そして事あるごとに「今度一緒にどうだ」「Y岩に来てくれ」「今日はこんなところを掃除した」と写真を送ってよこすのだ。他に話題はないのかというくらい、どんどん送られてくる岩の写真。どうも楽しくてたまらないらしい。
開拓の作業は重労働だが、「いい加減、歳も歳なんだから大人しくしていなさいよ」と言ったところで聞く耳は持たないだろうし、家族も皆諦めている。引退なんて言葉は、そもそも知らないのだろう。

撮影に向けて
企画会議に話を戻そう。
Y岩を提案してみると、半田さんも五十島くんも思いのほか興味を示してくれた。聞いたことのない岩場となると、食指が動いてしまうのはクライマーの性だ。
しかし提案しておきながら、僕もY岩には数回行った程度。初登攀を狙っているルートがあるわけでもない。岩場のスケールはどちらかというとこじんまりしているので、それこそAフランケのホットラインのように迫力あるショットが期待できるかも、正直分からない。そもそもY岩はほとんど未開拓に近い岩場だ。
以前父と行ったときには、自分で見出したルートを半分くらい掃除したところで日が暮れてしまったし、洗っても洗っても顔の穴という穴から黒いものが出てくるくらい埃まみれだった。汗と埃でどろどろの30過ぎの男を撮って、それが広告になる会社って、冷静に考えるとちょっと怖いぞ。
どうせ汚れるなら、いっそ挑戦的なことをしてみよう。そう思いついて、もうひとつ僕から提案してみた。
「手つかずのルートを、僕が『グラウンドアップ』で登るというのはどうですか」
「グラウンドアップ」は、未踏のルートをいきなり地面から登ること。つまり、上からロープにぶら下がって偵察することも、掃除することもナシ。そのルートがどれくらい難しいかも、岩が脆いのか硬いのかも、まるで分からない。未知の要素が詰まったクライミングスタイルだ。
出たとこ勝負なこの申し出にも、半田さんと五十島くんは乗ってくれた。
Y岩で撮影することに半田ディレクターからのゴーサインが出た後、父にその旨を連絡した。広告のコンセプトと併せて経緯を説明すると、
「面白い話です」
そして、
「Y岩に行くなら、同行したいです」
予想どおりの応えだった。
「積雪状況が怪しいかもな」
撮影の2日前、半田さんからそう連絡が来た。寒波の影響で、長野方面は数日前から雪が降っていたようだ。撮影日は晴れる予報だけれど、気温は上がりそうにないし、雪道になるだろう。それなのに、次の日から冬山に入る五十島くんが「できるだけ早く帰りたい」と言って、もともと決めていた現地の到着予定は午前6時。
Y岩の標高は1000メートル以上あるから、6時となると、マイナス10度とかじゃないか?早く帰りたいというのは、そりゃ僕だってそうだけどさ…という本音はひとまず隠して、どうにか説得して7時集合にしてもらった。

雪のY岩
撮影当日、岩場近くの林道へ車を乗り入れると、予想どおり真っ白だった。雪は深くないけれど、とにかく寒い。防寒着を着込み、足元は登山靴とゲイター。ほとんど冬山に入るときの格好になってしまった。
降ったばかりの軽い雪を踏みしめながら30分ほどで岩場に到着。日向で暖かく登れるといいな、という期待は見事に裏切られて、薄曇りで風が吹き、ダメ押しで雪も舞っていた。多分、誰かしらの日頃の行いが良くなかったんだろう。僕ではないと思うけど。
幸い、岩は凍りついていないようだったので、岩場全体を歩いて見て回りながら、どこを登るか検討することにした。壁の下を歩きながら、ルートとしての長さや見栄え、撮る場合のアングル、登って面白そうかなどを吟味する。
「あのクラック(岩の割れ目)、良さそうじゃないですか?」
「この壁だとちょっと短いよね」
「あそこをこうやって登ったらカッコいいじゃん」
「ここで右に行って、ちょっと登ったら左に戻って…」
半田さんも五十島くんも、それぞれの目線で岩を見上げて盛り上がり始めている。一方で僕は、登るのは僕なんですけど…と内心ひやひやするやら、緊張するやら。グラウンドアップで登る、というのを忘れちゃいませんか。
岩場のいちばん奥まで見て回り、入り口近くのオーバーハングしたクラックを登ることになった。傾斜はきついけれど、割れ目の幅が広いのでカム*は適度にセットできそうだった。
*カム:クラックに差し込み、墜落時にはロープの支点となりクライマーを守るクライミング器具。岩肌に打ち込まれたボルトと違い、このように自分でセットする器具はまれに外れてクライマーを守ってくれないこともあるのが恐ろしいところ。
来た道を入口の方へ戻っていくと、父が遅れてやってきた。
「おはよう」
「おはようございます」
挨拶と自己紹介もそこそこに、この岩場の開拓の経緯を2人に説明し始める父。Y岩への思い入れが、いつもより少し前に出ているようだった。
目当てのクラックの下まで戻り、壁を見上げる。
「おお、これを登るのか。怖そうだな」
父がそう口にする。これを登ると決めたら、なんだかさっきよりも傾斜が強く、壁も長く見えてくる。一方で、五十島くんはちょっと渋い顔をしていた。
「ここ、撮り方が難しいんですよね」
Y岩は斜面に突き出すようにある岩場で、地上から見上げる形で撮ると全体が潰れて小さく見えてしまうし、そもそも立つ場所があまりない。それに加えて壁の周りの木立が濃く、ツタが這っているところもあって、障害物がとにかく多い。つまり、「引き」で撮ることが難しいわけだ。
これまでの広告で撮ってきたような、圧倒的自然の中にぽつんとクライマーがいるという構図にはできない。うーん、どうしようか。
「とりあえず、上からぶら下がってみます」
五十島くんはロープを担いで岩場の上へと登って行ってしまった。

その後3人で集まって協議した結果、このルートは上からと下からの両方で撮るのが良さそうだ、という結論に落ち着いた。せっかく父が合流してくれたので、僕が登るときのビレイ*は父にお願いして、五十島くんだけでなく半田さんもカメラを構えることになった。
*ビレイ:地面でロープを操作し、墜落時にはクライマーが地面まで落ちないようにする重要な役割。
僕らが撮影のやり方を検討している間、父は自分で目をつけた壁をせっせと掃除していた。
「そろそろ、登るよ」
声をかけにいくと、壁に張ったロープを手際よく回収して下りてきた。
五十島くんは上から、半田さんは下から、それぞれ決めた位置でカメラを構える。僕はラジオ体操で体を温めた後、これから登るクラックを見上げて必要そうなギアを多めに用意し、ロープを結ぶ。
木下藤吉郎のように懐に入れて温めておいたクライミングシューズに、ゆっくり足をねじ込む。相変わらずの薄曇りで日差しは薄いけれど、風は少し弱まって気温が上がってきていた。それでもフリースは脱げないけれど、多分なんとかなるだろう。
「じゃあ、やってみよう。無理はしません」
「はい、とにかく気をつけて」
ビレイヤーの父と手短に声をかけ合う。

いざ、出たとこ勝負
撮影ポイントを探しながらルートを眺め回した印象では、おそらく5.10くらいの難度だろうと思っていた。5.10という難度自体は、普段の自分にとってはウォーミングアップの範囲内だ。しかし今は、ウォーミングアップを十分に出来ていないし、とにかく寒い。クラックに差し込んだ手の熱はあっという間に奪われて、感覚がなくなっていく。
グラウンドアップなので、当然岩は汚れている。クラックの中も外も、苔だか埃だかよく分からないものに覆われていて、上へ上へと手を伸ばすと顔にゴミが降ってくる。カムを慎重にセットして、試しに引いてみると、ガリガリッという音がして微妙にズレた。岩はそれほど脆くないけれど、表面はそこそこ風化しているらしい。
次に手を差し込むクラックの縁が、もしくは次に足を置く凹凸が、突然割れたりしないだろうか。頼むから、今は割れないでくれよ。そう念じながら一手一足を出していくと、次第に力が入って動きが硬くなる。呼吸も荒くなってきた。
「うっ…おおっ!」
怖さからか、息苦しさからか、自然と声が漏れた。クラックは途切れることなく壁にしっかりと切れ込んでいて、カムがほどほどの間隔でセットできることだけが救いだった。
オーバーハングがきつく苦しい中間部をフーフー言いながら抜け、その上に張り出したルーフ*の下に入り込む。このルーフを越えれば、壁の傾斜は一気に緩くなる。もう一踏ん張り。カムをセットしようと、行く手の視界を遮るように突き出たルーフを両断するクラックを覗くと、その向こう側に五十島くんの姿がちらりと見えた。ルーフを抜けた辺りにぶら下がって、こちらを覗きこんでいる。割れ目越しに一瞬目が合い、彼がカメラを構えるのが見えた。
*ルーフ:庇状に張り出した岩
多分、ここのカットだろうな。
シャッターを切る音を聞きながら、なんとなくそう感じた。
ルーフを抜け、幅の広がったクラックに体をねじ込み、やっと一息ついた。
「いやー、すごくワイルドだった!」
巨大なイワヒバに恐る恐る立ち上がったり、親指くらいの太さの灌木を引っ掴んだりしながら、どうにか壁の上まで抜けた。太い立ち木を見つけてロープを固定し、懸垂下降で地上に戻ると、一気に緊張が解けた。ビレイをしてくれた父に、礼を言う。
「長い時間ありがとう。怖かったー」
「よかったな」
そして父は「じゃあ、俺は帰る」と言って、荷物をまとめて下山していった。去り際に長く話さないのは、いつものことだ。

手と目
「開拓」というクライミングは、とにかく手間がかかる。新ルートを見出し、それを初登攀するまでには何日も、何十日も、ときには何年もかかってしまう。岩場を探すところから始めたら、それはもう途方もない労力が要る。たった1本のルートに何日もかかるというのは、ちょっと割に合わない。
未踏の壁ではなく既成のルートがたくさんある岩場に出かけた方が、1日に何本も登って楽しむことができる。掴んだホールドが脆くてギョッとさせられることも、頭から埃を被ることだってないかもしれない。今風に言えば、「開拓」はとてもコスパ・タイパが悪い。
でも、だからこそ僕はこのクライミングが好きなんだな、と思う。華やかさがなく、効率が悪いからこそ、一層好きだ。
手間がかかるということは、手を尽くさないといけないということだろう。今回のグラウンドアップでのトライは、事前の偵察や掃除という苦労はなかったけれど、そのかわりに未知の要素への不安が山盛りになって、自分の持てる引き出しをたくさん開けて登ることになった。精神もいくらか擦り減った。
それでも、誰も登っていない岩に出逢い、何が待っているか分からないところへ踏みこんでいくときの静かな高揚感が、僕の心を掴んで放さない。何日もかけて岩に向き合っても、あるいはグラウンドアップで一時の勝負を挑んでも、そこでは手を尽くした分だけ濃密な時間が流れている。
限られた時間でひとつでも多く、と欲張りたい気持ちをなだめながら、偶然見つけた岩には丁寧に手を尽くす。その時間、そして体験の濃さが、僕はとても愛おしい。
「お父さん、なんだか虫捕り少年みたいでしたね」
撮影の後、五十島くんがそう声をかけてきた。トレッキングポールを片手に岩場を歩き回る父が、虫捕り網を振り回してカブトムシを追いかける少年に重なったらしい。あの日、岩場にいた誰よりも、父の目が輝いて見えたのだという。
「このカットでほぼ決まりです」
そう言って見せられたのは、やっぱりあのクラック越しの写真だった。ばっちりカメラ目線なのが、ちょっと笑える。
「なんだかホラー映画っぽいな」
「ジャック・ニコルソンですか」
よく見ると、写真に写る僕の目が少しばかり血走っている。虫取り少年のような眼差しになる日は、まだ当分先らしい。![]()
五十島典空(カメラマン:ロストアロースタッフ)
この企画にかかわってすぐに気づいたのは、半田さんも自分も追い込まれてから動き出す性格だということだ。だから今回も広告の締め切りがわかったくらいで
「アレ?入稿もうすぐじゃないっすか?」
「あー、そうだな。あんまり時間がねぇな」
みたいなやり取りを始めた気がする。それと比べると渉さんは全てにおいて用意周到だから、どちらが進行管理をしているのかよくわからない時があった。
だいたい、演者に現場を案内してもらうディレクター・カメラマンという構図がおかしいのだけれど。その節は大変お世話になりました。
それから渉さんはもちろんのこと、お父さんの岳志さんにお会いできることも撮影隊の大きな楽しみだった。
「えええ、お父さん来てくれるんですか」
「いやぁワクワクするなぁ」
岳志さん出場の話題が、往路の車中で一番盛り上がったのは間違いない。
素敵な時間を共にしていただけたこと、最後にこの場を借りて御礼申し上げます。