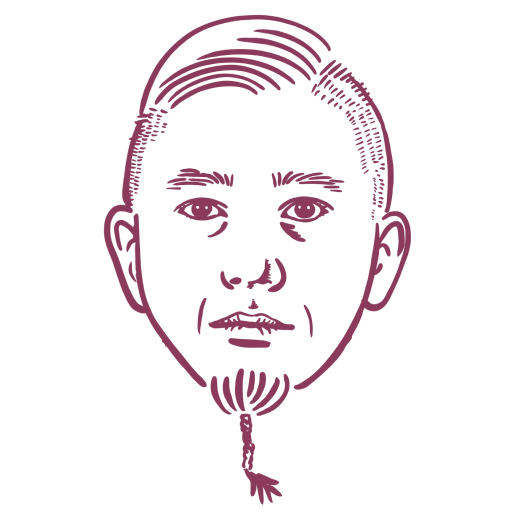「スタッフが登り、スタッフが撮る。」そんな写真を載せた雑誌広告が、現在までほそぼそと続いています。ここ「BEHIND THE SCENES」でご紹介するのは、最高のショットを求めて奮闘したスタッフたちの汗と笑いにまみれたクライミング記。今回は、『ROCK&SNOW』2023年秋号に掲載されたボルダリング課題「黎明」のストーリーを、ディレクターを務めた広告部スタッフの半田悠太が綴ります。特徴的な岩の形状と圧倒的な質量感、そしてロケーション。彼らが後に「これからの撮影にとって一つのベンチマーク」とさえ評した作品を巡る物語をどうぞ。
メンバー
半田悠太(ハンちゃん – 筆者):ディレクター:ロストアロー広告部
企画のディレクター兼サブカメラマン兼いざとなればサブクライマーというやや謎の立場。山の経験値は他の3人に比べて遥かに乏しく、基本的にはみんなに従っている。ディレクターにも関わらず。
五十島典空(テンちゃん):カメラマン:ロストアロー広告部
クライミングと名のつくものはすべてエンジョイ。写真やギアの造詣に深く、ひとつ話を振ろうものなら100返ってくるのが長所でも短所でもあるが、写真の腕は確か。
大木輝一(テル):今回の被写体:ロストアロー営業部
今最も脂がのったクライマーの一人。バイタリティに溢れ、クライミングから山岳スキー、沢登り、キャニオニングと数々の冒険を深く追求する男。思い切った発想と実行力とたまに思い切りすぎる言動をするロストアローの斬り込み隊長。
ロケハンデート
2023年7月25日、梅雨明け。
同僚のテルから聞いた話を頼りに、僕と相棒のカメラマン、テンちゃんはまだ朝日が差し込み始めたばかりの林道を歩いていた。目的地はこの奥にあるはずの2つのボルダーだ。
どうしてここに向かうことになったのか。今となっては記憶もあやふやだが、次の撮影ターゲットを探していた僕らにテルが話しかけてきたのがキッカケだったような気がする。彼は少し興奮気味に「これとかどうですか」と僕の顔の前にスマートフォンの画面をぐいっと突き出してきた。そこには、彼が沢登りをしている時に発見した2つの巨大ボルダーが写っていた。
ボルダー[Boulder]とは英語で「大きな石の塊」や「巨岩」を意味する。高さ3m〜5m、時にはそれ以上のサイズの岩を対象にして、それらをロープを使わないで登ることをボルダリングという。
テルに見せてもらった画面には確かに見栄えしそうな巨岩——ボルダーが写っていた。ボルダラーの自分としては刺さる写真だったのだが、次は山の中の壁を撮りたいとディレクターとしての自分は思っていた。これまでボルダーの写真は撮ってきたから、ステップアップしたいというわけだ。だから画面のなかのボルダーは今求めているものと少し違うかもと思っていたのだった。

とは言え、今回の広告に使わないにしても見栄えする岩なのは確かだ。今後いずれ撮影することになる可能性だってある。岩そのものはもちろん、周辺環境、日の当たり方、撮影ポジションなど確認しておきたいことは多い…。岩やクライマーの魅力をどこまで写真に残せるかは、実際現地に行って見てみないとわからないことが多いのだ。運が良ければぶっつけ本番で撮影までいけてしまうこともあるが、「こりゃねーな」で帰ることになるリスクはなるべく避けたい。
ということで、他にも候補に上がった岩場と抱き合わせで、まずはカメラだけ持ってロケハン—偵察に出かけることにした。まあでも、もしかするとあわよくば撮影までできちゃうかもしれない——だから念の為シューズとチョークをバックパックに忍ばせた。あくまで念のためだ。まさか途中で遊ぶためにシューズを持っていくわけがない…。
計画ではまず、午前中のうちにアプローチの遠い方の岩をチェックする。そして車で移動したあと比較的近い方の岩に向かうことにした。
靴底のゴムも溶けそうな都心の猛暑とは打って変わり、早朝の山中は7月末でも肌寒いくらいだった。時折カラッとした風が爽やかにそよぎ、足取りは軽快だ。
歩いていると現れる岩壁に登れそうなラインを妄想したり、恐らく自分が生まれる前から廃れたであろうトンネルの中でキャッキャと撮影会を交えながら意気揚々と足を進めた。

対面
渡渉まじりの片道1時間半のコースをこなし、首尾よく1つ目の岩の偵察を終えた僕らは一路2つ目へ。こちらも片道1時間弱の道のりではあるが、登山の時間感覚で言えばあっという間だ。そろそろ岩がありそうな雰囲気だから川の様子でも見るかと立ち止まって周囲を窺ったところ、いきなり目指す岩と対面することとなった。
スマホで見た岩とはぜんぜん違うじゃないか。
テルから写真を見せてもらったとき、当時求めていた撮影対象と違ったというのは前述したけど、実は正直言って形状についてもどうもピンとは来なかった。広角レンズの影響で横方向に歪んだ岩にはそこまで迫力が感じられなかったのだ。
ところがこの実物の岩!
真夏の午後のギラつく太陽を浴びた巨岩は、初見のインパクトが凄い。そして岩を取り巻く空間の完成度も凄い。一気に鼓動が高まる。まさにキングボルダー。
印象的な形状の高さ10mを超える岩が、ゴーゴーと絶え間なく音を立てる滝の飛沫を浴びながら滝壺のプールに鎮座している。ぱっくりと平らに割れたダイヤモンド状に広がる面は、まるで誰かが設計したかのような美しさだ。
河原にあるまんまるな石ころや水たまりの波紋、蜘蛛の巣や貝殻の螺旋。ランダムな自然の中に、幾何学的なような、人工的なような形を見つけると美しく思うのは一体なぜなんだろう。
僕のパソコンのAIによると「自然界の不規則性の中に、予期せぬ秩序や完璧なパターンを発見すると、脳はそれを効率的に処理できるため、心地よさや喜びを感じます」だそうだ。僕の脳が効率的に働いたかどうかはともかく、クライマーでなくとも一見の価値ある風景だ。信仰の対象となってもおかしくないなどというと言い過ぎだろうか。

さて、ところで果たしてこれは「登れる」対象なのだろうか?疑問がむくむくと頭に湧いてくる。
8mほどある平らな面の傾斜は80度くらいだろうか。垂直よりも少し向こう側へ岩の面が寝ている。下部から真ん中あたりまでは体を安定させられそうな形状を確認できるが、墜落時のリスクが高まる上部は目視する限り手がかりが掴めない、未知に近い領域だ。登るテクニックやフィジカルといったスポーツ的要素よりも、墜落リスクを受け入れてそれでも未知の領域へと登る覚悟こそが問われる課題といった印象を受けた。
岩の下はプールのようになっていて、想定着水ポイントは水深2m以上はありそうだが、最上部からの墜落に耐えられるのか?着水ポイントを左右に外せばほとんど剥き出しの岩盤が待っている。
日差しに焼かれた岩は石鍋のように熱く、岩に触れた指先がじわじわと汗で湿ってくる。自分が登る姿を何回想像してみても、指先が汗でズルりと滑ってしまうイメージが頭から離れない。上部で落ちたらと思うとゾッとする。よし。とりあえず暑い日中の撮影は避けよう。写真的にも夏の日差しは明るすぎる。
テルの作法
情報をくれたテルが沢登りの遡行中にこの岩に出会ったのは冒頭に述べた通りだ。そしてさすがは斬り込み隊長。その後早々に訪れ、すでに何度かトライ&ドボンしたそうだ。しかもロープを固定してぶら下がり、上から事前に岩の偵察や掃除、練習をすることもなくである。
この男、ハートが強すぎる。
真摯にトライする彼の話を、同じクライマーとして尊敬の念が湧き上がるのを感じながら、そして燃え上がるジェラシーを抑えながら聞いていた。

今回の撮影では安全を考慮して、ぶら下がって事前練習してもらうことも検討したが、なにしろ被写体として登るのはここまでロープを使わずトライを重ねてきたテル本人である。決して無理しないことを約束に、彼が望む取り組み方(グラウンドアップという登り方)を尊重することにした。
なんでロープを使わないことにこだわるのか、という疑問を持つ方もいることだろう。もっともだと思う。話すと長くなってしまうので手短な説明ではあるが「極力道具に頼らず、未知の部分を残して冒険性を大切にする、精神性に重きをおいた登り方が好きだったから」と言えば伝わるだろうか。
生暖かく、肌寒い風
はたして偵察から1週間後の早朝5時前、被写体のクライマーであるテルを加えた3人は例の岩の前に立っていた。陽の光が入るのを待ちながらカメラマンのテンちゃんはそそくさと機材をセットしている。今回の機材はカメラ2台三脚2台についでに僕の自前のコンデジ。
テンちゃんはこの日のために新しい三脚を買ってきたようだ。2mの高さがありカーボンなのにコスパがいいなどといつものように自慢してくる。機材の多さに対してクライミングのギアは靴とチョークだけ。ボルダリングでは着地用のマットを敷くのが一般的だが、今回はもはや敷くことができないので持ってこなかった。落ちたら滝壺のプールにドボンというわけだ。
気温は前週と同じくらい。早朝—今の時間は長袖で少し肌寒いくらいなので登るコンディションとしては上々だ。逆に冷たい沢への着水を想像すると胸がきゅっとなる。
午前3時半に起きた僕は、生暖かいような肌寒いようなどちらともつかない風を感じる緊張に加え、絶え間ない滝の音が入り混ざり、妙なトランス状態になっていた。

見守るしかない
すでに15分は超えている。
ゴーゴーと落ちる滝を横目に、テルは岩に張り付いていた。踏ん切りがつかないのか、行く先を見いだせていないのか、岩の平らな面で進んでは戻り、戻っては進みを繰り返している。頂点に至るまでに可能性を感じられる道筋はいくつか考えられるが、未知であるが故にどのラインを辿ればいいのか、それとも引き返すべきなのか、全てクライマー自身の判断に委ねられている。
足下に冷たい川と岩盤がある状況では、一か八かで進むにはリスクが高すぎてどうにも割に合わなそうだが、時には大胆に進むことで状況を打開できることもある。テルは今、岩の表面のごく小さな形状の変化を指先やつま先で繊細に感じ取り、体重をかけ、テストすることで、ぼんやりとした頂点までの地図の解像度を高めている。
しかし見ているこちらはたまったもんじゃない。彼の集中を乱すまいと極力声はかけないように黙ってシャッターを切り続けていたが、長い緊張感に耐え切れず「そろそろ一旦降りてレストしたほうが…」の言葉が喉元まで出かかったその時。
テルは意を決したように今までトライしなかったライン取りで一気に進みだした。彼特有の素早い動きで数メートル上がったところで最後の未知を確認している。すでに簡単には戻って来られないであろうポイントオブノーリターンを超えている。
一手一手進んでいく間、僕は何度もシャッターを切りながら、ファインダー越しに唱えた。
「絶対落ちるなよ」
そしてほんのちょっとだけ「俺が先に登るから落ちろ」と。
天に願いが通じたのか通じなかったのか、せんべい布団のような厚さの苔がのったリップを抑え、テルは岩の上に這い上がった。
冒険の妥協点
「黎明」この一枚の写真は撮影プロジェクトに携わるテンちゃんと僕の二人にとって重要な意味を持っている。未知への冒険性、緊張感、自然の豊かさ、写真としての完成度。どれをとっても今までの撮影やこれからの撮影にとって一つのベンチマークとなっている。
後日談だが、テルがいつものカレー屋で昼飯を食べながら、今回のクライミングについて突っ込んできた。
「でもカメラが有ったって意味では、冒険性が薄れているんですよね」
僕は一瞬まさかと思ったが、冷静に考えれば確かにそのとおりだ。カメラマンがいることで、事故時にも誰か対応してくれる人がいる安心感をもたらし、心理的負担を軽減しているということだ。

靴を履く、チョークを使う、ロープで安全を確保するなど、クライミングは数ある妥協の上に成立していると思っている。どこまで妥協を許すかは強制するものでもされるものでもなく、クライマー本人次第だ。登り方は自由に選ぶべきとは思うが、この写真を見て登る意欲を掻き立てられたクライマーに豊かな冒険をしてもらえたなら、僕らにとっては素晴らしいことだと思う。![]()