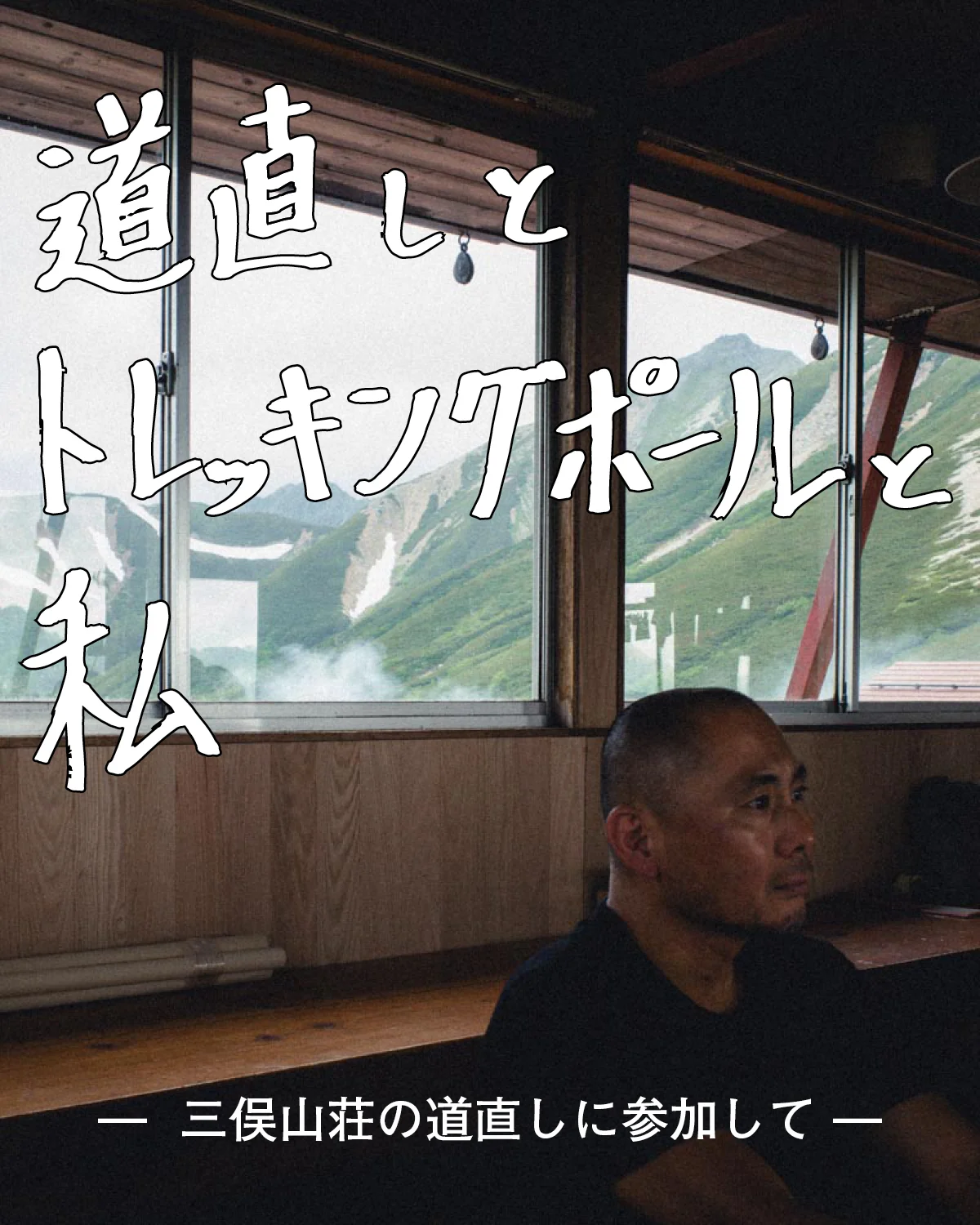北アルプスの三俣山荘が主催している、登山道修復・整備作業の「道直し」プロジェクト。歩き方やトレッキングポールの使い方や気象など様々な要因で引き起こされる登山道の崩壊を食い止め、持続的で自然な景観を取り戻そうという取り組みです。2025年7月上旬に行われた「道直し」にロストアローからも2名のスタッフが参加しました。今回手記を寄せたのは、まさにそのトレッキングポール販売の中核を担っていた営業部スタッフの橋本龍平。自ら身体を動かし、風景に包まれながら、販売との内なる葛藤、そして子どもの頃の自然への根源的な経験にまで思いを馳せたようです。
6月末から続く猛暑の中、埼玉にある事務所を出発し、松本インターで高速を降りた。
新島々を抜けると、車の窓から流れ込む風は山の匂いが濃くなってくる。
この山の空気、匂いの移り変わりが山に向かっているという実感を伝え、気持ちが切り替わってくる。
明日は三俣山荘までの長い道のりだ。
なるべく朝早く出発するために今日は新穂高の民宿に前泊をする。部屋にはエアコンはない。外の空気は涼しく、扇風機だけでも寝苦しくはなく、すぐに眠りに落ちた。

伊藤さん、石川さんとの出会い
2025年1月中旬、三俣山荘の石川さんから電話をいただいた。トレッキングポールの使用が周辺の植生に影響を与えていること、特にブラックダイヤモンドのZポールが顕著であることをお話しされ、東京の事務所でお会いして詳しくお話を伺うこととなった。
直接お会いすると、山荘を取りまとめる伊藤敦子さんの道直し(登山道修復・整備作業)にかける熱い思い、そして石川さんの静かな語りに引き込まれていく。登山道の浸食の話や、道直し中にもその脇で悪気なくトレッキングポールを植生に突く登山者の話などを聞くにつれ、これはトレッキングポールを販売する側として実際に現場を見て考えなければいけないと感じた。私たちはその場で、7月の道直しに参加することを約束したのだった。
入山
新穂高温泉から三俣山荘まではコースタイムで10時間近い。16時からのオリエンテーションに余裕をもって間に合うよう、出発は4時にした。夏至から10日ほどしかたっていない7月4日は、4時と言えどもすぐに明るくなってくるので、ほとんどヘッドランプはいらない。
雪崩で通行止めになっていた左俣林道の土砂は重機で片付けられて通れるようになっていた。夏山シーズン前ということもあり、秩父沢に架かる橋などもなく登山者にすれ違うこともない。鏡池に映る槍ヶ岳を見ながら鏡平を抜け、弓折分岐の手前にまだ残る雪渓をチェーンスパイクでトラバースして順調に進んだ。
15年ほど前、私はバックカントリースキー中に雪崩に巻き込まれ、前十字靭帯を断裂し再建手術をした。その後の半月板の手術や、緩んでしまった前十字靭帯の再再建手術と膝に3回メスを入れていて、長い距離を歩くときはどうしても膝に不安があり、トレッキングポールが必需品になってしまっている。
双六小屋を抜け、三俣山荘への巻道は残雪が多そうなので中道を進むと『風景と道なおし』*にあった複線化した登山道が出てきた。これは、もともと1つだった登山道が歩きにくくなったりして、それを避けて別のルートが出来てしまう状態のことだ。これまでに見かけた方も多いだろう。
二つに分かれた道は狭く、ポールを使えば当然両脇の植生にポールを突くことになる。ポールの真ん中をもって使わずに行くと、藪の中からシカが飛び出してきた。
*『風景と道なおし』:三俣山荘が制作・販売している冊子。「道直し」の背景や考え方などを知る第一歩となる。
標高2700mの高山帯に鹿がいる!これにはかなり驚いた。
シカは丹沢などで問題になっているように植生に与える影響が大きい。デリケートな高山帯ならなおさらだ。たまたま迷い込んできただけならいいのだが…。自然環境の変化をまざまざと見せつけられた気がする。三俣蓮華岳の頂上では雷鳥のつがいが仲良く砂浴びをしていた。近づいても全く逃げない。これも夏山シーズン前の登山者が少ないこの時期だからだろうか。
今回の道直し参加者の中では、私たちが最初の到着だった。夕食の後のオリエンテーションでは、アウトドア業界の方を対象とした道直しは初めてなこと、三俣山荘の登山道管理範囲は40kmと広大なこと、山深い場所なので資材やスタッフも含め道直しは困難なことなどの説明があった。

自然観察会
2日目、朝食後に三俣山荘から三俣蓮華岳方面の登山道周辺で自然観察会が始まった。
ハイマツに囲まれたトンネルを昨日通ったのだが、これは登山者が歩くことで地面が掘れていき、トンネル状になったとのことだった。トンネル側面の土は元々の地表面なので非常にもろい。ここをポールで突けばすぐに土壌が崩壊してしまうだろう。
登山者が歩くことで道は浸食され、そこへ水が流れると浸食はさらに進む。登山者は侵食されて歩きにくくなった道を外れるようになり、道が複線化する。複線化すると元あったお花畑は分断され、島のようになる。
分断された島がトレッキングポールで突かれるとさらに裸地化が進行する。しかも島はトレッキングポールで突きやすい位置にあったりする。一度裸地化が進行すると、植生が戻るスピードよりも水による浸食のほうが早く、なかなか元には戻らないのだそうだ。
裸地化が進行したことで20年間閉鎖されていた登山道の跡も見せていただいた。
植生回復の土留めを施した部分は植生が戻り始めていたが、施工していない場所の植生は戻ってきていない。そして20年たっても植生はほんの少ししか回復しない。
休憩を特別に草原の上ですることになった。正面に鷲羽岳を望み、とても気持ちのいい風と景色の中、座った地面からは柔らかな感触が伝わる。どれぐらい土の厚みがあるのか見てみると、土壌はとても薄い。10cmもないんじゃないだろうか。
そして、家の周りの草地でよく見るミミズや虫などの分解者が土の中に極端に少ないことに気が付いた。つまり枯れた植物の分解が進みにくく、土壌ができにくい。高山の土壌は圧倒的に脆弱で傷つきやすく、回復力が弱いのだ。私は草原に座りながら、山登りや自然に親しみ始めた小さいころを思い出していた。


私と自然と登山
子供のころ、高校の生物教師だった父に連れられ、父の友人たちが建てた山小屋によく行くようになった。その山は、今ではバックカントリースキーで有名になり、週末ともなれば多くの人が訪れる人気エリアとなった鍋倉山である。
1985年頃、鍋倉山を訪れる人は少なく、冬ともなれば訪れるのは山小屋の人だけだった。その鍋倉山にブナ林の伐採計画が持ち上がった時、この美しいブナ林を守るために山小屋の関係者が立ち上がり、鍋倉山のブナ林調査が始まった。
子供だった私は大人が入っていけない藪にメジャーを引っ張って測量の手伝いをしたことをよく覚えている。今思えば、大人は褒めてくれるし、単純に楽しい遊びの一つだったことは確かだ。藪をこいでいると足の下にはブナの葉が厚く積もり、その分厚くやわらかな土壌の感触をよく覚えている。
そして、土の中には様々な生き物がいた。ブナの木に「水」と鉈目が刻まれているブナもある。ブナ1本、田一反と言われるほどブナは土壌に水を貯えるのだ。
このころ私は蝶の採集に夢中だった。森の梢の上をエメラルドグリーンの金属光沢が煌めきながら踊るように飛翔する、小さな宝石のように美しい蝶「ゼフィルス」。これを採集するために口径60cmのシルクでできた捕虫網を、5mの竿の先につけ森の中を歩き回る(この竿は今、雪崩ビーコン講習会の仕事で活躍しています)。
彼らゼフィルスを見つけるためには蝶の分布、生活、食草を知らなければならない。自然と木の名前や森林の構造を私は覚えていくようになっていた。このころは山登りというよりも自然の中で自然自体を楽しんでいた時代だった。
その後私は高校、大学と山岳部にいたことで、夏山縦走から始まり冬山、クライミング、バックカントリースキーへと活動が移っていった。自然そのものを楽しむことから、山でのアクティビティを楽しむように徐々に変わっていった。大学では山に近いという理由で農学部の森林専修を選んだ。研究室は砂防。桜島の巨大な砂防工事を見学し、土石流危険渓流に人が住む場所での砂防ダムの重要を知り、土壌の浸食や森林内での水の移動を学び、卒論は斜面角度による雪の積もり方や積雪の破断強度に関する研究を行った。土壌の浸食に関する基本的な知識もあったはずだった。

ロストアロー入社後とトレッキングポール
卒業後は今の勤務先、ロストアローに入社。入社から数年が経過した2007年から、ブラックダイヤモンドのトレッキングポールの取り扱いが始まった。
ゴム製石突きカバーの「ティッププロテクター」は、海外では今も昔もトレッキングポールに付属しておらず別売りだ。だが当時から日本では植生保護のために「ティッププロテクター」を付属して販売することは一般的だった。そのため、倉庫に製品が入荷した後、私たちはトレッキングポール一本一本に手作業でティッププロテクターを付けて販売を始めたのだった。
販売数が伸びてくると今度はティッププロテクターを倉庫で取り付ける作業量が膨大になり業務を圧迫し始める。そこで、日本向けにあらかじめティッププロテクターを工場で付けてくれないかブラックダイヤモンド社に相談し、最低発注量とコスト増をクリアすることで発注ができるようになった。
2011年には、ブラックダイヤモンド初の折り畳み式トレッキングポール「Zポール」が発売される。
「Zポール」はブラックダイヤモンド社の持つバックカントリースキーギアの設計技術を応用した革新的な製品だった。
「Zポール」は軽量化のため石突きが細いので、従来のティッププロテクターを付けることが出来なかったが、先端を金属ではなくゴム製にすることで地面を傷つけにくいような配慮がされてもいた。
販売開始後もティッププロテクターがないことによる問題を指摘されることはほぼなく、数年後にはZポール専用のオプション「Zポールティッププロテクター」も開発された。
ところが2022年、Zポールのモデルチェンジを境に石突きがゴム製から金属製に切り替わった。従来のゴム製の先端は、ゴムが摩耗しきった状態で使い続けると石突き全体まで摩耗してしまい、下段シャフト全体の交換につながるケースがあったからだ。
石突きが金属製になることで「Zポールティッププロテクター」を製品に付属させることも検討したが、
- 付属によるコスト増
- 最低発注数量のクリアの問題
- 「Zポールティッププロテクター」の販売数をみると、多くのZポール購入者がティッププロテクターも購入していると推測されること
- 環境省に問い合わせたとき、環境省としてプロテクターの使用を推奨はしていない、各現場の判断という回答があったこと
- 登山道の草刈りが大変なのでポールで突いてもらった方がいいという話も聞いていたこと
- ポールによる土壌浸食の論文* がないこと
などから「Zポールティッププロテクター」の付属化を私たちは見送った。
*北海道大学大学院環境科学院の2025年3月の論文によればトレッキングポールのプロテクター有無による土壌への影響を調べた論文が発表されている
https://envgeo.ees.hokudai.ac.jp/2025/03/02/trail-surface-experiment/?utm
しかし、この判断は正しかったのだろうか?
本当に植生への影響はないと言えるのだろうか?
作業が増えることや、コスト増を言い訳にしてはいないだろうか?
自分に都合の良い言い訳を探していないだろうか?
私の中にはモヤモヤとしたものがこれまでずっと残っていた。
伊藤さんのお話の中で、ブラックダイヤモンドのZポールが金属製の石突きむき出しでティッププロテクターをしていない人が多く、植生を破壊しているという話を聞いた時、私はその場では平静を装っていたが大きな衝撃を受けていた。その一方で「本当にそうなのか」という信じたくない気持ちがあったのも事実だった。だが実際にこの目で現場を見ることで、もはや疑いようのない現実を突きつけられた思いがした。

道直し
初日の午後と翌日は黒部五郎へ向かう巻き道の道直しを行う予定になっていた。
3班に分かれ作業を開始。オリエンテーションの時に見た写真や『風景と道直し』を読むことで、どのような作業をするのかはなんとなく理解しているつもりだった。
しかし、実際に現場に立つと、どこをどうすればいいのか、どこから手を付けていいのかが見えてこない。そして、その場にある石を利用して道を整備するため、圧倒的に資源が少なく、雪渓の上の岩場から石を降ろしてこなければならない。
それでも何とか作業をはじめ、水や雪の浸食に耐えられるアンカー石を見つけ、水の流れを変えて洗堀を防ぐように石を配置するなどするうちに雨が降ってきた。ずぶ濡れになりながら1日目の作業が終了。
雨は夜半まで降り続いた。
作業2日目
昨日の午後の雨は嘘のように晴れ朝から快晴。引き続き同じ場所で道直しの作業を進める。岩場で採った石を雪渓を滑らせて降ろし、背負子に入れて、投げて運び続け、水の流れ込む場所には砂防ダムのように砂を受け止め、貯めるような段差構造を作り、トレッキングポールが植生を突かない位置かつ登山者が自然に歩けるように石を飛び石のように配置した。
道直しも作業者の性格や考えが色濃く出てくる。
私たちの班は雪や水の浸食に耐えるよう大きな石を使うことでゴージャスな道となった。一日作業を終えて振り返ると、進んだ距離は10mほどだ。なんて地道で時間がかかり、そして頭と体をフル回転させる作業だろう。これを40kmも整備しなければならないことを知った私は、もう雑に道を歩くことはできなくなった。
下山しながら考えた
この2日間、三俣山荘の周りの自然を見て、道を直すことで、植生の見え方と歩き方が明らかに変わり、私は「Zポール」にティッププロテクターを付属させることを心に決めた。
でも、それだけでこの問題は解決するのだろうか?
確かに「Zポール」にティッププロテクターを付属させることで植生へのインパクトは軽減されるだろう。しかし、軽減されるからと言って植生にポールを突けば、程度の差はあれ浸食は進行する。
では、トレッキングポールを売ることを辞める?
それも解決にはつながらないと思う。私たちがトレッキングポールの販売を辞めても、並行輸入品を販売する人は出てくるだろう。その並行輸入品は海外で売られているポールと同じだから、ティッププロテクターはついていない。
私たちがトレッキングポールの販売を辞めることで逆にティッププロテクターなしのポールが増えてしまうかもしれない。これも無責任かと思う。
私たちロストアローが直接的にできることは、トレッキングポールにティッププロテクターを付け、植生への影響を軽減することだけど、それだけではこの問題が解決するとは思えない。
この山に関わる全ての人が高山帯の植生、土壌の脆弱性を知り、理解し、道の成り立ちや誰が整備しているのかを知ること。そしてトレッキングポールの使う場所や使い方を考え、実践すること。そういう動きが広がって、少しずつ解決に向かっていくのではないかと私は思う。
そのために私たちもできることをすすめていくつもりだ。
この美しい風景が、私たちの後から来る人たちにも見てもらえるように。![]()