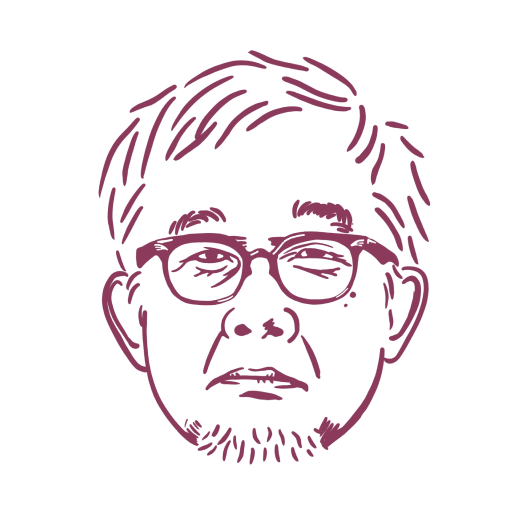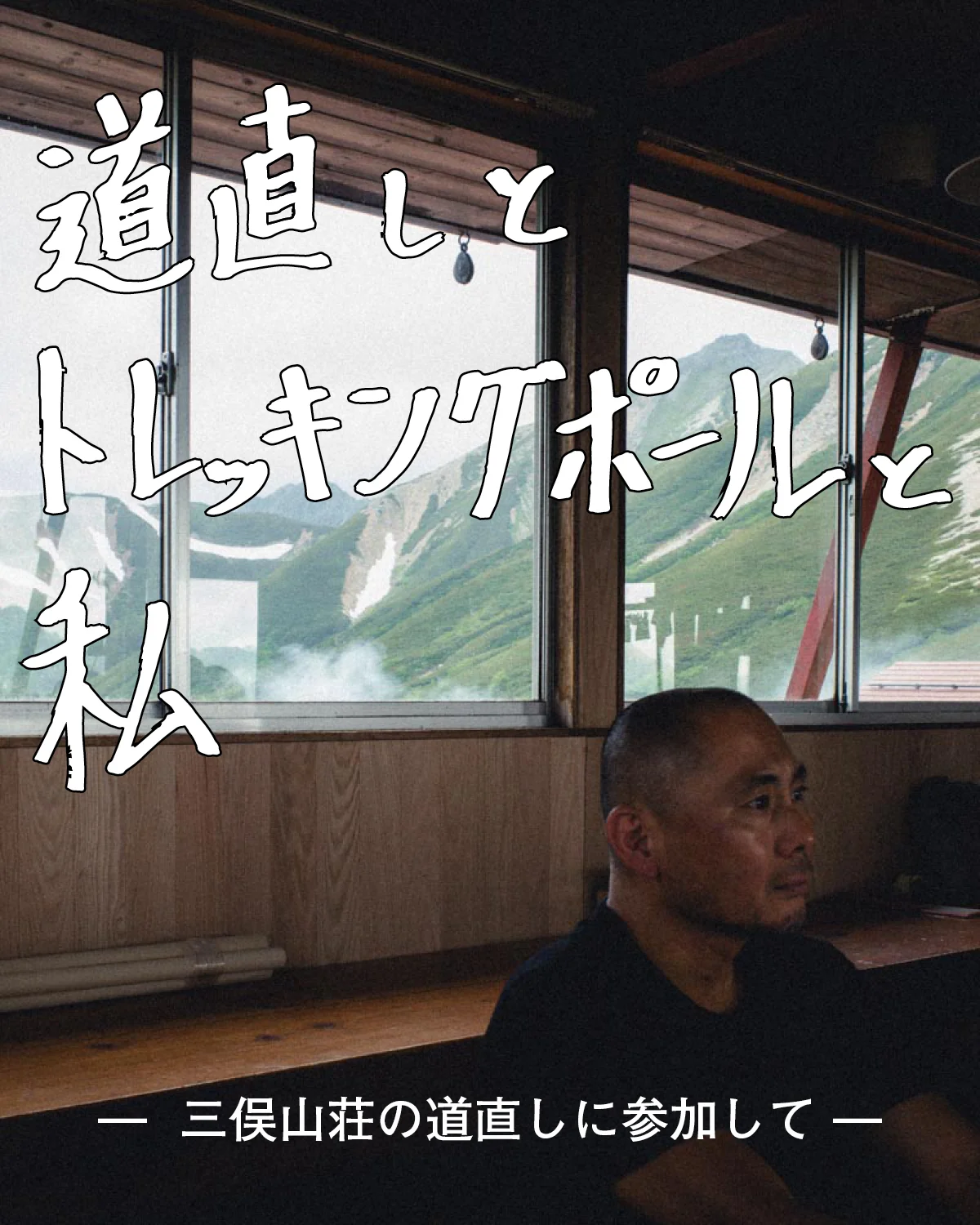ロストアローが輸入販売する登山・クライミング・スキー用製品のほとんどは修理可能で、その大半は自社内の修理部門が担っていることをご存じでしょうか。それは破れた生地の縫製やファスナー交換に留まらず、登山靴のリソールやカムデバイスのトリガーワイヤー交換に至るまで、ほとんどすべてに及びます。なぜロストアローは製品修理に力を入れているのか——。その理由を数回にわたって、寺倉力さんがレポートします。初回は「スカルパ」の登山靴修理です。
スカルパ本社での異例の修理研修が実現した
「イタリアのスカルパ本社に行って、登山靴修理の研修を受けてみませんか?」
砂田直樹がロストアロー修理部門に転職するきっかけとなったのは、このひと言だった。砂田は前職で15年、ロストアローに移ってから6年と、20年以上登山靴修理に携わってきた筋金入りの職人である。

実家は、かつてオリジナル登山靴の製造・販売で知られた店だったが、砂田が物心つく頃には、請け負いの登山靴修理一本にシフトしていた。大学時代はソフトテニスの選手として県大会で優勝。卒業後は一般企業を経て、家業である登山靴修理工場に入った。
そこから、寡黙な父のもとで登山靴修理のイロハを学ぶことになる。最初は、登山靴に木型を入れて靴ひもを結ぶといった簡単な作業から始まり、1足を任されるようになるまでは3年を要したという。
そんな砂田にイタリア本社行きを打診したのは、スカルパの正規輸入販売会社であるロストアローの代表・坂下直枝だった。
当時、坂下は自社の登山靴修理体制を根本から見直そうと模索していた。その一環として、次代を担う修理人をイタリア本社に送り込み、本場の高度な技術に触れてもらおうと考えた。そして、スカルパ修理の外注先のなかから、当時30代だった砂田に白羽の矢を立てた。
もっとも、この坂下のアイデアがすぐに実現できたわけでもない。というのも、砂田はスカルパ以外にも、複数の登山靴メーカーの修理を並行して請け負っていたからだ。
複数のブランドから仕事を請けるのは、日本の登山靴修理業界では一般的な慣例だった。だが、スカルパ社にとっては、自社技術が他社へ流失するリスクがある以上、簡単に受け入れられることではなかった。しかし、そこは坂下とスカルパ社との長年にわたる信頼関係と、そして誠意ある交渉が功を奏し、異例の本社研修が実現するに至った。

そんな修理で納得できるはずがない
日本では多くの海外登山靴ブランドが、修理作業を外部の職人や工場に委託している。その大きな理由は、修理を自社内で行おうとすると、設備投資や人件費を含めたコストが割に合わないからだ。
さらに、日本では登山靴を扱える修理工場が限られているため、一つの工場が複数ブランドの登山靴修理を請け負うのは当たり前となっている。ブランドごとの独自性が損なわれるというデメリットも、現状では甘んじて受け入れてられている。
たとえば、交換用パーツについては、各ブランドから専用のものが支給される場合もあるが、必ずしもすべてのモデルに対応できるだけの在庫が揃っているとは限らない。そのため、実際の修理では、どんな登山靴にも使える汎用パーツを代用するケースが多く、結果としてオリジナルデザインに戻らないことも珍しくない。
また、修理工場では1足あたりの修理代が基準になるため、効率良く数をこなすことが最優先されがちで、そうした職場環境のなかで、仕上がりのクオリティを追求するのは難しいのが現実だ。
加えて、ユーザーから預かった修理品はショップの店頭からメーカー(または輸入代理店)、そこから修理工場へと送られ、修理後は逆コースで返送される。そのため、ごく簡単な修理であっても、時間も送料も二倍三倍に膨らんでしまう。

「登山靴修理とはそういうものだと思っていたフシがありました」と、ロストアロー代表の坂下は当時を振り返る。当時の国内の登山靴修理の実情は、どこも似たり寄ったりだったからだ。
その認識を一変させたのは、一人のユーザーから届いた長文のクレームだった。ソール張り替え修理を終え、手元に戻ってきた登山靴を見て、そのユーザーは憤慨したのだ。
「ひと言でいえば、こんな修理では納得がいかない、というお叱りでした。でも、それ以上に、修理対応の不備——引いては、登山道具を扱う会社としての姿勢そのものを問う、厳しい内容でした」
愛着のある登山靴を修理に出したのに、ちぐはぐな色や形になって戻ってきたら……。次の休みに山へ行こうと修理に出したら、「納期は数カ月後」と告げられたとしたら……。
「一人の登山者の立場になってみれば、すぐにわかる話です。そんな修理で納得できるはずがない。はっと胸を突かれる思いでした。そこからです。修理を根本的に見直そうと決めたのは」

日本の”当たり前”を改善したいという思い
長年、登山靴修理を生業にしてきた砂田にとって、スカルパ本社での研修はまたとない機会だった。「ぜひ行かせてください」と即座に快諾した砂田は、坂下とともにイタリアへと渡り、北イタリアにあるスカルパ本社工場を訪れた。
そこでの数日間の研修を通して、砂田は日本との違いに目を見張ることになる。それは、靴職人として十分な経験を積んできた砂田だからこそ、なおさら痛感した彼我の差だった。
「本社の技術の高さは圧倒的でした。まず、木型を入れるところから違うんです。接着剤の塗り方ひとつもそうですし、しっかりマスキングテープを貼ることや、周囲のゴムを傷つけないような削り方など、一つひとつの作業すべてが明らかに違った。なかでも最大の違いは、修理人としての意識の高さです」

意識の高さとは、具体的にどういうことだろうか。砂田はこんなふうに話してくれた。
「たとえば、紙に3本の線を書いてくださいと言われたら、私たちは普通に3本の線を書くと思います。けれども、それがスカルパだったら、しっかり定規を当てて、均等な直線を3本引く。その違いです」
丁寧に、手間を惜しまず、時間をかけて直したものをお客様に届けたい——。そんな意識が修理工程の至るところに散りばめられていたと、砂田は言う。
たとえば、ソール交換の際に靴に木型を入れる最初の作業では、事前にスチームでアッパーを温め、木型を差し込んで靴ひもをしっかり結び、アッパーのシワを丁寧に伸ばす。
たとえば、古いランドラバーを剥がす工程では、本体が熱によるダメージを受けないように、部分ごとにヒートガンで優しく温めながら、時間をかけて丁寧に剥がす。
また、ランドラバーを貼るために接着剤を塗るときには、必ずマスキングテープを貼り、不要な接着剤のはみ出しを防ぐ——。

これらはほんの一例に過ぎないが、そのどれもが、長く使える靴に仕上げるための、当たり前の配慮だった。けれども、それらは日本ではあまり馴染みのない作業ばかりだという。
たとえば、アッパーのシワを伸ばさなくてもソール交換に支障はないし、接着剤がはみ出しても後から削り取ることはできる。だが、それをやるかどうかで、仕上がりは段違いに変わる、そんなひと手間の積み重ねばかりだったと、砂田は振り返る。
「そこまでやるのか、という驚きがありました。クオリティを求めるとなると、やはり各工程で少しずつ手間が増えていきます。けれども、それらのなにか一つでも欠いたら、いい仕上がりは望めない。私がスカルパ本社で痛感させられたのは、まさにその点でした」
本社工場の修理部門は専任が3、4人で、彼らの作業場は、生産ラインの真っ直中にあり、手が足りないときは、生産担当のスタッフが修理を手伝うこともあるという。削る、塗る、貼る——。靴作りのあらゆる熟練作業に、生産と修理に境目はなく、互いに競い合いながらも、よりいいものを届けたいというクラフトマンシップが職場全体に満ちていた。
そんな本場の職場を、心の底からうらやましく思うと同時に、これまでの自分の仕事を深く省みるきっかけにもなった、と砂田は語る。
「今までのやり方で本当にいいのだろうか。それは、自分に誇れる仕事といえるのだろうか——と」。

帰国後ほどなくして、砂田は坂下との話合いを経て、ロストアローへの入社を申し出ることになる。それは長男として家業を支えてきた砂田にとって、どれだけ重い決断だったことか。そう思わずにはいられない。
「スカルパ本社で修理人の高い意識と技術に触れ、こんな環境で働きたいという思いが芽生えました。帰国後、坂下さんとお話をさせていただくなかで、日本では当たり前と思われている修理の現実を、少しでも改善したいという坂下さんの思いがひしひしと伝わってきました。ならば、私も修理人としてその思いに参加したい。そう思って、ぜひ一緒に働かせてください、とお願いしました」

国内唯一のスカルパ公認リペア工房の誕生
砂田の入社に際して、坂下はスカルパ本社とできる限り同等の修理環境を整えることに注力した。それこそが、登山靴修理のクオリティを引き上げるために欠かせない条件だと考えたからだ。そのため、砂田の草案をもとに、設備からパーツに至るまで、さまざまな準備が整えられた。
なかでも特筆すべきは、交換用パーツの徹底した備えである。ソールユニット、ランドラバー、フックといった交換用パーツは、すべてスカルパの純正部品でそろえ、しかも過去10年ぶんにわたるモデルの部品を可能な限りと取り揃えた。
たとえば、登山靴「リベレHD」のランドラバーに4色のバリエーションがあるとすれば、すべての色をもれなく用意する。さらに、新製品が発表される際には、たとえデザイン変更がわずかであっても、アップデートされたすべてのパーツを欠かさず仕入れる。デザインは登山靴にとって顔ともいえる存在。その印象を損なわないための配慮でもある。



交換用パーツは、ソール交換可能なスカルパ登山靴の全ラインナップに及び、フックなどの小物類を含めると、その在庫数はおよそ9,000点にのぼる。
これは、正規輸入代理店であるロストアローだからこそ実現できた体制といえる。もっとも、すべてのパーツが実際に使われるわけではないため、回収できない部品代も相当な額にのぼるはずだ。
また、修理環境の整備においては、イタリア本社で使用されている最新機材を導入した。ソールを削るためのグラインダー、剥がしや接着に欠かせないオーブン、接着部分をしっかり固定する圧着機……。どれも高精度な修理作業を支える重要な機材であり、この点も従来の日本の修理現場とは大きな差があった。
なかでも、精度の高いソール交換を支える要ともいえるのが圧着機だ。これは、スカルパが独自開発した特殊な機材で、わざわざイタリアから輸入されている。

この特殊な圧着機は、上下からの水圧を利用してプレスする仕組みで、従来のように平面的に押しつけるだけの圧着機とは異なり、登山靴全体を包み込むように、全方向から均一に圧力をかけることができる。
そのため、ソールユニットやランドラバーを含むすべての接着面にムラなく圧力が伝わり、確実な接着が可能になる。また、靴に木型を入れたままプレスすることで、アッパーのシワが伸ばされ、仕上がりの美しさも格段に向上するという。
ちなみに、この圧着機一台の価格は、あの”赤い跳ね馬”で知られるスポーツカー1台分に迫るという。登山靴修理の品質向上にかける、ロストアローの本気度がうかがえるエピソードといえるだろう。
こうしてロストアロー社内にスカルパ専用の修理工房が整備されたのが2019年のこと。イタリア本社から認定を受けた日本国内唯一の「スカルパ・オーソライズド・リペア・ファクトリー」の誕生である。![]()
後編に続く
写真=柏倉陽介